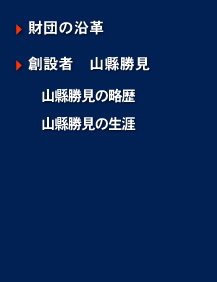≪山縣勝見の生涯 その3:戦後日本海運ゼロからのスタート≫
昭和20年(1945) 8月15日終戦となった時点で、わが国に残された船舶は、船舶運営会の調査によると873隻150万8,000総トン(大正初期の水準に相当)、このうち就航可能な船舶は100万総トンに満たず(日露戦争当時に相当)、その多くは粗悪船、老朽船でした。戦争中の船腹喪失総量は実に829万総トンに達し、開戦時の保有船舶に戦時中の新造船などを加えた約1,000万総トンに対して実に83%が喪われた計算になります。
日本の非軍事化を目的とした占領政策では、占領と同時に全日本船舶の移動を禁止し、100総トン以上の船舶は全て総司令部の指揮に従うべきことを指令するなど、日本海運の復興を厳しく抑制する方針を示し、又戦時補償交付も打ち切られましたので、海運業の前途は暗黒でした。
昭和21年(1946) 11月に発表されたポーレー賠償委員長の米国大統領に対する対日賠償最終勧告案は、5,000総トン以上の船舶を賠償の対象とし、日本の船腹量を極東の貿易に必要な鋼船150万総トンに限り、更に船型・速力・建造量などにも制限を加える厳しい内容でした。山縣はじめ海運界首脳は、日本経済自立のためには、何をおいても日本海運を再建すべきであり、そのためには外国航路への就航を禁止すべきでなく、船型・速力などについても制限を加えるべきでないことを、関係方面に強く訴えました。
財閥解体指令により、辰馬汽船株式の65%を所有する辰馬本家商店が昭和22年(1947)地方財閥に指定され、解散することになった為、辰馬汽船は辰馬家との資本関係がなくなりました。山縣社長は会社再建への熱意に燃えて社員から新社名を募集しました。こうして選ばれた新社名「新日本汽船(株)」は、「世間から支持を得られる立派な会社」、「財閥から離れて民主的に運営される会社」を念願する海陸従業員の気持ちを高め、新生日本にふさわしい社名として終戦直後の挫折感と低迷を払いのける大きなきっかけになったのです。
その後、米国の対日海運政策においては、米ソ両陣営間の「冷戦」が激化するにつれて、日本をして反共への防壁たらしめるために、むしろその経済を自立せしめ、その潜在的な軍事生産力を活用せんとする考えが米国の世論に急速に芽生えました。そして昭和23年(1948)に入って対日管理政策の再検討が行われ、ガリオア・エロアによる物資の供与、民間貿易の許可及び企業の集中排除の緩和などの政策に現われました。
そして最大の懸案であった「日本船舶の賠償取立問題」も昭和23年(1948) 5月の「ドレーパー報告」にて、船腹保有量と船型等の制限を撤廃し、民間造船施設を賠償の対象から外すとされ、一挙に決着することになりました。
しかし日本船舶の本格的な外航航路復帰にはまだまだ一波乱を経ねばならなかったのです。